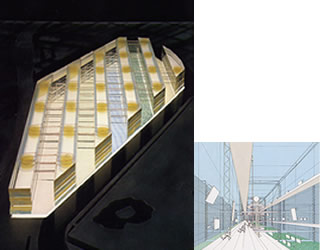ゴシック的「美術状況を作る」とか「アーティストを育成する」という言い方がある。日本の現代美術状況を語るときに頻繁に使用され、それなりの幻想的な説得力を行使する言語でもある。しかし、私が発案した「日本美術館構想」はこのような概念を前提としたものではないことをここで今一度明確にしておかなければならない。美術状況は作るものではなく、「ある」もので、「アーティスト」は「育成される」ものではく「存在するもの」であるからである。
裏を返せば「美術館」という機構自体を支えてきた前提はこのような概念だったかもしれない。つまり、作品の収集、保管によって「作品」という「情報」と「価値」を管理し、「状況」を統制しながら制御していく、そして生まれるべきアーティストの方向を決定づけていく。メルロ・ポンティはヘーゲルの概念体系を批判を込めて「哲学の美術館」と呼んだそうだが、そこになぞられるように、近代における美術館は神の権力から逸脱した人間たちが美という形而上的な概念までをも統御しようとした証と見ることができる。
「日本美術館構想」は、西洋近代主義のプロセスの中で育まれた「美術館」というゴシック的な価値観を持つ概念から脱走しようとする計画である。それは近代主義すら一つのヴァナキュラーになってしまうボーダレスの時代にあって、そのもっとも象徴的な「美術館」という概念(ここではあくまで建造物ではなく概念と呼ぶことにこだわりたいと思う)の中に「横断的」で「対話的」な概念と価値を持ち込むことによって積極的な矛盾をひき起こす。
しかし、概念でありながら美術作品(もしくは主観的にその範疇にふくまれるものすべて)という現実にかかわるものを扱う機構において、どのようにそれを具体化すればよいのだろうか。その鍵はやはり建築と、そこに含まれる機能そしてトポスという次元においえて発見されるべきであろう。
現在、世界に実在する美術館群の中で近代美術館の原風景を提出するものを取り上げるとすれば、次の三つの美術館があげられるだろう。ルーブル美術館、ベルリン美術館、ポンピドー文化センターである。そして、その差異の中に今回の構想に対するヒントが含まれていると思う。
ルーブル美術館はよく知られているように、もともと王宮であったものが封建制の崩壊とともに美術館へと変貌していく近代的なプロセスの端緒の一つとなったものである。そしてその成り立ちゆえに都市交通の起点の象徴、およびアイデンティティカルなランドマークとしての役割を今でも果たし続けている。
ルーブルに代表されるかつての封建的な建築物の美術館の流用は「機能」のすり替えと、社会価値の保護のシンボルという意味において近代主義的な美中t巻の出発点を示唆している。
つまり、極端な言い方になるかもしれないが、封建制の後、「王」という存在、もしくは価値にかわってそれを代行したのは流動的な「議会」や「大統領」ではなく基本的な「価値」を「保管」する「美術館」だった、とはいえないだろうか。その視点においては、美術品は、いわば、体制権力のシンボルであり、ゴシック的な価値の積み上げを具現するものであったはずである。そうすると、「王宮」は便宜上「美術館」に流用されたのではなく、その「場」と「価値」において必然的に選択されたという見方もできるに違いない。そして「美術館」における永遠に持続される「新しい価値」の収集とその保管への機構、機能の改良、インデックスの細分化は西洋近代主義の基準であり続けている、といっても差し支えないと思う。最近完成し、世界中を驚かせたルーブルの大改造計画もその原点からみれば、むしろ必然的な経緯であった、というほかはない。
そのような近代美術館像を「王」立場から実現させようとしたものがベルリン美術館である。「美術館島」と呼ばれるように一つの島を四つの美術館で覆う、という壮大な計画はプロイセンの王ウイルヘルム三世によって発案されたが、潜在的な構造からみれば封建制と近代民主主義の狭間にあってその折衷を王の側から図ったものであるとみることができる。その意味では「大英博物館」と同種のものである。すなわち、抽象的な価値を単機能な建築物によって具体的な価値へとすり替え、しかも「王」と「大衆」の中間に置こうとした半公共機関なのだ。このような美術館の建築は実際は王権の誇示という次元のものではなく、言わば、価値の部分的な放出と機能、制度化を用いて「近代」と折衷しようとした封建権力の延命策と捉えたほうがより現実的である。それは、その後のドイツ帝国の隆盛と崩壊、大英帝国の推移をみても明らかなことだ。そして、その現象は、マクロ的に見れば、ルーヴル型の美術館の機能の転回点や、ワシントン・ナショナル・ギャラリーをはじめとするアメリカ型の美術館の成立経過にあてはめるとより明確に理解できるはずだ。
トポスの革命;「現代の価値」を視覚化する美術館建築
「美術館」に全く新しい次元での価値を提案した、もしくは潜在的にある価値を抽出した、といえるのはピアノ=ロジャースによるポンピドー文化センターではないだろうか。
中央市場の跡地再開発計画の一端として計画されたこのセンターは美術館という社会の価値基準の一つをさらに大きく、しかも抽象的な価値で包むという、言い換えれば、企画自体が近代主義の中での価値の見直しを意図したものである。そしてそれは建築それ自体によって最も明確に語らえたのである。
「王宮」の価値と象徴の流用、権力のすり替え、といった過去の成立要因だけではなく、美術館が美術館としての価値の獲得を模索し、実現したのは恐らくこのポンピドー文化センターが初めてのものだろう。
ここでピアノ=ロジャースはフランク・ロイド・ライトによるグッケンハイム美術館において行われた小さな実験を拡大し、完成している。それは交通と消費、そして機能の集合を明確で、しかも仮設的な形で表現することである。逆に言えば、彼らは「美術館」という概念を支えてきた抽象的な権力をこの三つのファクターに分解し、総合したのである。
このセンターは建築物というよりむしろ、一つの機械と見た方がいいだろう。価値というものを永遠に生み出しながら消費する機械、そして、そのプロセスこそが実は現代の価値である、それが彼らの設計意図に違いない。視覚的に明確にそのコンセプトを表現し、そして、機能においては徹底的に仮設製を追及することで美術、もしくは文化に時代的な価値、つまり流動的な価値があることを明らかにしたのである。機械の完成度が高ければ高いほど、その作業自体が概念化される。ポンピドー文化センターはまさにそのような機械なのだ。
さらに付け加えると、ポンピドー文化センターはまさにそのような機械なのだ。さらに付け加えると、ポンピドー文化センターは「美術作品」と「美術館」を概念的に始めて切り離したものといえる。すなわち、そのコレクションがいかなるものであろうと、美術館はその存在と機能によってアートと文化を表現できうるという意図がここには見えるからである。
都市のダイナムズムを損なうことなくその循環するエネルギーを吸収し、交通させる。そして、知識とエネルギーのあくなき吸収と排泄を機械的に視覚化することで文化の一断面を都市の中に実現しているのである。つまり、パリというトポスの中で文化という抽象的な概念を視覚的にフィールド化しているのである。このことこそ、その後の美術館建築にあっても最も重要な原因として残り続けているものなのである。また、機械的にそれを達成することによって地球上のいかなる都市においても文化の違いを超えてそれが可能なことを告げるものでもあった。
極論を言えば、今私たちは美術館が美術品と袂を分かたなければならない、という矛盾を持つ時代の中で「美術館」を発想しようとしている。それは、「美」というものが機能や物質ではなく形而上的な概念に戻ろうとしている時代でもあるからである。
行く先を失っていた「美」が、究極的な多様化とエコロジーの波の中で、復活しようとしている神々のもとへ戻っていこうとしている時に、果たして「美術館」は可能なのだろうか、その概念は必ずついて回るに違いない。
しかし、かつての教会がそうであったように人類に美を知覚させると、これからの美術館より一層「場」を追求するものでなくてはならない。バウハウスは芸術の最終目標は建築だ、と宣言したが、やはり美術館においてもその最後の鍵の一つは、確かに建築家たちが担っているようである。
今回、第二次「日本美術館構想」最終回において、最初の設計を依頼した鈴木エドワード、そして若手建築家の精鋭・竹山聖、隈研吾の三氏に集まってもらったのはこのような思考の経緯によるものである。彼らには先に述べたエコロジー(もしくはトポス)と芸術の多様化という状況を前提にする以外何の制約もなしに発想してもらうことにした。それは発案者自身にも残る「美」の常識から彼らを解放するためでもある。
(SCAPE21 1993-1月号)